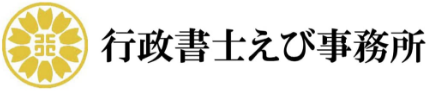認知症と診断された場合の生前対策
事例集
2025.09.29
~これからの暮らしと財産を守るために、今できる選択を~
近年、認知症の発症は誰にとっても他人事ではなくなってきています。
ご本人が認知症と診断されたとき、
「これからの生活はどうなるのか?」
「財産や不動産の管理はどうしたらいいのか?」
ご家族には多くの不安がのしかかります
■まず確認したい:「判断能力」の程度
認知症と診断されたとしても、すぐにすべての法律行為ができなくなるわけではありません。
重要なのは、「本人にどれだけの判断能力が残っているか」という点です。
たとえば初期の段階であれば、医師の診断書などにより、
まだ一定の契約行為が可能とされる場合もあります。
【例】
・ 不動産の名義変更・贈与
・ 遺言書の作成(公正証書)
・ 任意後見契約の締結
これらの手続きが可能かどうかは、医師の診断書やご本人の面談内容によって判断されます。
そのため、できるだけ早めにご相談いただくことが大切です。
■判断能力が不十分とされた場合の選択肢
もしもすでに「判断能力が不十分」と判断された場合でも、法的サポートを受けることができます。
成年後見制度(法定後見)
家庭裁判所に申立てを行い、ご本人の代わりに財産管理や契約手続きを行う「成年後見人」を選任してもらう制度です。
後見人は、以下のようなことを代わりに行います
1.預貯金の管理
2.不動産の維持・管理(※売却には別途許可が必要)
3.各種契約手続き(施設入所など)
>ポイント:一度後見人がつくと、ご本人の財産管理はすべて後見人の同意が必要になります。
ご家族による不動産の管理・売却
認知症と診断されたご本人が所有する土地や建物について、「空き家になるから売りたい」「管理が難しくなった」といったご相談も多く寄せられます。
ただし、本人が判断能力を失っている状態では、原則として勝手に売却や契約はできません。このような場合は、次のような対応が必要です。
・法定後見制度を利用し、家庭裁判所の許可を得て売却
・信託契約など、過去に手続き済みの場合はその内容に従って処理
>ご家族の意思だけで不動産を売却することはできませんので、専門家に必ずご相談ください。
・よくあるご質問
Q. 成年後見人には誰がなれるの?
A. ご家族がなることも可能ですが、状況によっては司法書士や弁護士などの専門職が選ばれることもあります。
Q. 成年後見を申し立てると、すぐに不動産を売れる?
A. 売却には家庭裁判所の「許可」が必要です。申立てから決定までは通常2~4ヶ月ほどかかります。
Q. すでに認知症が進行しているが、遺言は作れますか?
A. 医師による診断書があり、遺言作成時に意思能力があったことが証明できれば、公正証書遺言の作成が可能な場合もあります。
・当事務所のサポート内容
当事務所では、以下のようなサポートを行っております:
・ 成年後見制度の申立書類作成・申立て代理
・ 医師との連携による意思能力の確認・診断書取得サポート
・ ご家族との面談による不動産の今後の方針相談
・ 空き家・土地の管理や活用方法のアドバイス
・ 相続・名義整理までトータルで支援
法律だけでなく、不動産の売却や管理の現場にも強い行政書士事務所だからこそ、生活に密着した具体的なご提案が可能です。
最後に:できることは、まだあります
「もう何もできないのでは…」と不安に思われるかもしれません。
ですが、認知症と診断されたあとでも、できること・選べる選択肢は必ずあります。
大切なのは、「ご本人とご家族の意思を大切にしながら、今後をどう支えていくか」を一緒に考えることだと言えるでしょう。